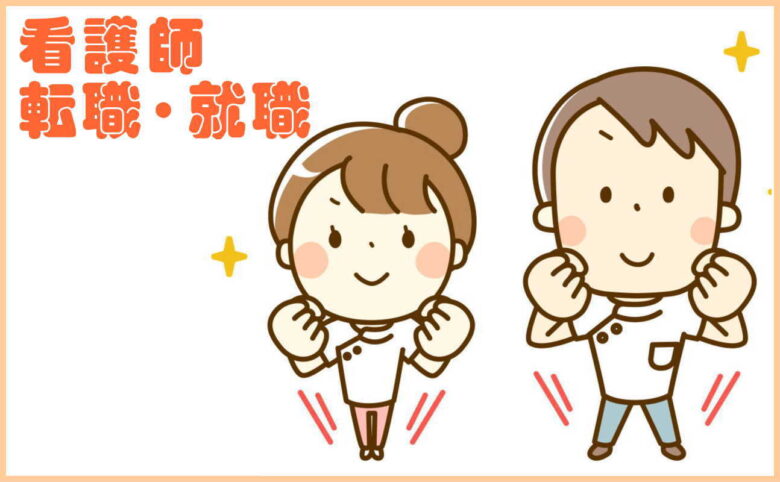こんばんは♡
看護師ねふなです
勤務復職に向け
知識整理をしました
組織の成功循環モデル
をお伝えします
1.組織の成功循環モデル

MIT組織学習センター
共同創始者
ダニエル・キム教授に
よって提唱されたモデル
業績の結果だけを求め
行動してしまうと
組織の人間関係が悪化し
業績が落ちてしまうと
いう場合が多くあります
結果を追い求めるのではなく
心理的安全性の高い
環境づくりや目標共有
メンバーの主体性や
相互理解に基づいた
役割分担を心掛けることで
遠回りしているよう
ですが結果も向上します

2.組織の成功循環モデル4つの質

4つの質
「組織の成功循環モデル」
組織を4つの要素で捉えます
1.関係の質
相互理解や信頼関係があり
オープンなコミュニケーション
を取ることができる
2.思考の質
理解が浸透しており
アイデアがたくさん出る
3.行動の質
積極的に効果的な
行動をとり新しいことを
取り入れることができる
4.結果の質
目標を達成する
高い成果・業績を得る
これら4つの質の要素は
その質が循環し作用しあいます
3.バッドサイクル・グッドサイクル

質の循環はバッドサイクル
グッドサイクルの
2種類に分類できます
バッドサイクル
関係・思考・行動
結果の質が相互に
マイナスの影響を
与え合い循環している状態
結果を追求し目先の
業績を向上させようと
することから始まります
無理に成果を出そうと
命令・対立・押しつけが
生じ関係の質が低下します
関係の質が下がると
思考の質と行動の質も
同様に低下します
メンバーが受け身になり
積極的な行動をしなく
なると成果は得られません
結果の質の低下は
人間関係をさらに悪化
悪循環に陥る原因となります
短期的に業績が向上する
可能性はありますが
持続可能な発展は
期待できません
グッドサイクル
関係・思考・行動・結果
の質が相互にプラスの
影響を与え合い
循環している状態
組織の関係の質を
高めようとすること
から始まります
メンバー間の相互理解と
尊重を深めることで
快適なコミュニケーションが
実現し思考の質と行動の質が向上
自発的に考え行動する
メンバーが増えれば
業績も向上し
結果の質が高まります
これによりさらに
関係の質も向上し
良い循環が続きます
グッドサイクルを
実現するためのステップ
目先の結果にとらわれず
グッドサイクルの起点となる
関係の質をはじめ
思考の質と行動の質を
高めることが重要です
4.関係の質向上方法

関係の質向上方法
グッドサイクルに
欠かせない関係の質を向上
させるコミュニケーション
心理的安全性
人間関係を構築するには
十分なコミュニケーションが必要
組織内で発言しても
周囲から拒否されたり
罰せられることなく
自然体でいられる環境は
新しいアイデアや考えを
自由に発言する上で重要です
心理的安全性について詳しくはこちら
組織で心理的安全性を高める方法
気軽なコミュニケーションを
増やしお互いのかかわりを自然に増やす
挨拶を積極的にする
気軽な世間話をする
関わりがある人に
感謝の気持ちを伝えてみる
相手の仕事の状況に
ついて聞いてみる
気軽なコミュニケーションを
通してチーム内のつながりを
強くし心理的安全性を
高めることで組織としても
個人としても課題解決の
スピードが上がったり
モチベーションが上がることで
関係の質を上がります
相互理解
メンバー同士の考え方や
状況について理解を
深めることが重要です
仕事の役割や立場を超え
個々が相互理解を深める
ことで信頼を築き組織の
結束力を強めることができます
5.思考の質向上方法

思考の質向上方法
目標共有
関係の質を向上させるには
良好な関係構築や
相互理解だけでは不十分です
組織における理想の
関係には求められている
ことを共有する
ことが必要不可欠です
各メンバーが組織の
目指す目標やビジョンを
理解し共有すること
組織の最終目標に
貢献するために思考し
行動することが求められています
メンバー全員が納得し
追求できる目標を設定し
共有することが欠かせません
目標を共有することで
発生した新たな気づきや
課題を共有する仕組みを
整えることも有効です
具体的には1on1の面談や
定期的な会議を意図的に
設けることで目標達成に
向けてモチベーションが向上
6.行動の質向上方法

行動の質向上方法
主体性
結果を得るためには
目標や価値観に向かって
全員が積極的に
行動する主体性が重要です
VUCAの時代・組織に必要な
スキルを理解し
自分で取捨選択する
ことも必要です
※VUCA
目まぐるしく変転する
予測困難な状況
Volatility(変動性)
Uncertainty(不確実性)
Complexity(複雑性)
Ambiguity(曖昧性)
主体性が発揮される条件
1.目標共有
全員が組織の目的や
目標を理解できている
2.役割分担
自分が遂行すべき業務や
役割を理解できている
3.相互理解
メンバー同士それぞれの
考え方や特性を理解し合えている
4.心理的安全性
失敗やミスに対して
責めるのではなく
受け入れられていると感じる
役割分担
各自の主体性を向上
させるために重要
目標の共有・相互理解
心理的安全性が必要な理由
目標共有
業務や役割は組織で
共有している目標を
達成するために
分担を決めるため
相互理解
メンバーそれぞれの
強みや弱みを活かし
または相互に補完
できるように分担するため
心理的安全性
安心してコミュニケーション
取れる環境でこそ
個々の能力が発揮されるため
適切な役割・業務分担が
行われていない場合
優秀な人間の業務量過多
フリーライダー
仕事をしていないにも
関わらず賃金を得ているが現れる
定時で帰れる人
残業する人に分かれる
責任の所在が分かりづらい
ストレスで離職率が増える
関連記事はこちら


前回の記事

復職に向けて
知識整理をしました
今回は
組織の成功循環モデル
についてお伝えしました
前回記事も
ごらんくださいね♡

看護師ブログ:ねふなHappyワークライフバランスは現役看護師がネフローゼ症候群発症し職場復帰を目指し奮闘する日々を綴っています。
初めて入院にまで至ったネフローゼ症候群について、入院の経緯、療養生活の不安などをお伝えして、少しでも同じ症状の方の療養生活や看護や仕事の悩みの参考になればと思っています。
看護の知識もちょっとずつまとめてアウトプットしています。
また、異業種を約10年働き再び看護師復帰をした経験もあります。
看護師以外の方へも仕事の悩みや日々をHappyに過ごす参考に少しでもなればと思っています。
仕事選び転職サイトはこちら↓↓