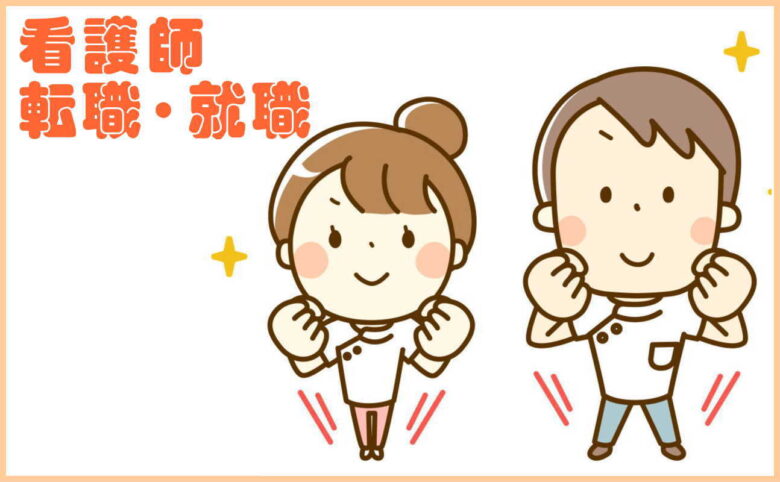こんにちは♡
ねふなです
看護提供体制
について
書き込んで
みたいと思います
看護提供体制

患者に対してどのように
看護を提供するかという
組織的な仕組みである
看護提供体制について
まとめています。
1.看護提供体制の要素

看護提供体制の要素
看護方式(看護提供の方法)
固定チームナーシング方式
Partnership Nursing System(PNS)
機能別看護方式
受け持ち看護方式
人員配置
看護師の人数やスキル
夜勤・日勤の体制
看護補助者の配置
役割分担と責任体制
リーダー看護師
チームリーダーの配置
業務分担の明確化
誰が何をするか
看護記録や情報共有の仕組み
電子カルテや申し送りなど
カンファレンス体制
患者中心のケアを支える仕組み
継続看護
入院〜退院〜在宅まで
チーム医療との連携

2.目的と最近の傾向

目的
安全で質の高い看護の提供
患者の満足度向上
看護師の働きやすさの確保
バーンアウト防止
最近の傾向
PNSの導入拡大
タスクシフティング
タスクシェアによる効率化
ICT(情報通信技術)の活用
3.固定チームナーシング

固定チームナーシング
Fixed Team Nursing
看護師をいくつかの「チーム」に分け
チームごとに特定の患者を継続的に
担当する方式
チームにはリーダーがおり
看護計画立案やメンバーの調整を行う
特徴
継続性があり
患者との関係が深まりやすい
チーム内で情報共有ができ
メンバー育成や指導がしやすい
看護の質をチーム単位で管理できる
メリット
看護の一貫性・個別性の向上
経験の浅い看護師を
チームで支えられる
責任の所在が明確で
リーダーシップが育つ
デメリット
人員配置や勤務表に柔軟性が必要
チーム間の情報共有が不足すると
連携に支障が出ることも
4.パートナーシップナーシング

パートナーシップナーシング
Partnership Nursing System
2人1組のパートナーで
1グループを構成し
共に患者を受け持つ方式
例:主に経験看護師と新人
または中堅同士
特徴
同じ患者に対して、常に同じペアが
ケアを実施
経験や知識を補完し合うことで
教育的な効果も高い
メリット
新人教育が自然に行える
情報共有が密で、観察力や判断力の
向上につながる
患者から見ても、担当者が安定して
いる印象を受ける
デメリット
パートナー間の相性や関係性に
影響されやすい
一方に負担が集中すると、不平等感や
ストレスになることも
5.混合型(固定チーム+PNS)
固定チームとPNS比較
| 項目 | 固定チーム | パートナー シップ |
| 単位 | チーム (複数名) | ペア (2人) |
| 継続性 | チームでの 継続的関わり | ペアでの 継続的関わり |
| 教育性 | チーム内での 指導 | パートナー 同士での指導 |
| 柔軟性 | やや低い (チーム構成による) | やや高い (個々の勤務調整が要) |
| 患者視点 | 担当チームが 把握しやすい | 担当者がより 明確にわかる |
混合型(固定チーム+PNS)
チーム単位で患者を受け持つ
チーム内でPNSを基本単位として
業務を行う
特徴
継続性のある看護
チームが同じ患者群を継続して
受け持つため継続看護が可能
協働による安全性の確保
PNSにより2人で確認・実施することで
ヒヤリハットやインシデントの予防が
できる
教育的効果
経験年数の異なる看護師が
ペアになることで
OJTが自然に行われる
柔軟な人員配置
チーム内でのPNSペア変更などが可能
業務量や能力に応じた対応がしやすい
責任の所在が明確
チームリーダーとPNSペアが
明確な役割分担を持つことで
責任の所在がはっきりする
例
日勤帯:PNS体制で業務実施
1年目+3年目の看護師ペア
夜勤帯:チーム内での個別受け持ち
+協働支援
※カンファレンスや申し送りは
チーム単位で実施、情報共有を重視
留意点
PNSを固定ペアにするか流動ペアに
するかは施設の方針による
チーム内コミュニケーションと
信頼関係構築が成功のカギ
経験差やスキル差による
業務負担の偏りに注意が必要
関連記事はこちら

前回記事はこちら

病院勤務復職に向けて
知識整理をしました
今回は
看護提供体制
について
お伝えしました
前回の記事も
ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき
ありがとうございます
看護師ブログ:ねふなHappy
ワークライフバランスは
現役看護師が
ネフローゼ症候群発症
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や仕事に
悩む方の参考になればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする情報
提供できればと思っています