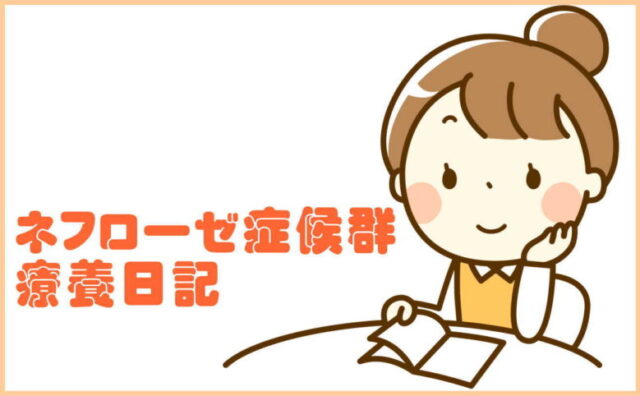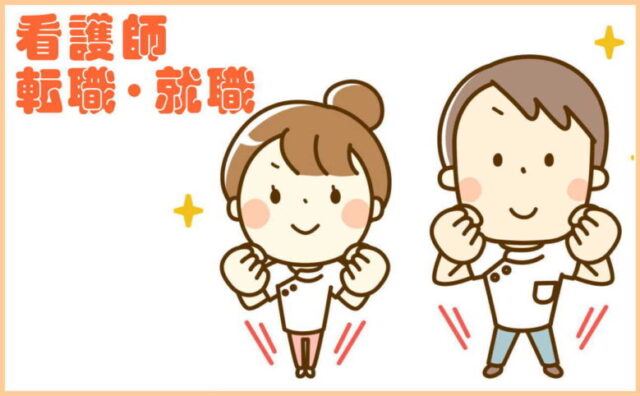こんにちは♡
ねふなです
ネフローゼ症候群と
安静について
お伝えします
ネフローゼ症候群と安静

ネフローゼ症候群罹患し
入院、自宅療養生活で
必然的に活動量低下
安静についてまとめています
1.ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群
原因
糸球体の透過性亢進により
血中タンパク質(主にアルブミン)が
尿中に漏れ出る
症状
大量のタンパク尿(3.5g/日以上)
低アルブミン血症
全身の浮腫(特に顔・下肢)
高脂血症
二次的合併症
感染症(免疫低下)
血栓症(凝固亢進状態)
腎機能悪化
2.安静の目的

安静の目的
日本腎臓学会
ネフローゼ診療ガイドライン
治療導入期やネフローゼ状態が
持続する場合は高度の運動制限を
要するとされている
激しい運動が蛋白尿を悪化させる
可能性が指摘されている
海外ガイドライン
むしろ動かないことによる血栓リスクが
高いため、絶対安静は推奨していない
| 目的 | 詳細 |
| 浮腫・蛋白尿の軽減 | 立位や歩行により 重力で水分が下肢に 移動し浮腫が悪化する 安静による腎血流抑制 で一時的に蛋白尿が 減ることがある 急性期に安静は有効 |
| 腎機能の保護 | 活動で腎の血流や圧が 変化し負荷がかかる ことで、症状の悪化を 招く可能性がある |
| エネルギー節約 | 浮腫が強い急性期は 活動疲労を避ける |
| 感染・再発予防 | 免疫が抑制されやすい 疲労やストレスが 加わると感染症や 再燃リスクが高まる |
| 深部静脈血栓症(DVT)予防 | 急性期は出血リスクも 考慮される 長期の運動制限は DVTを誘発しやすい 入院中でも下肢運動や ストッキングの 使用が推奨される |
| QOL維持 | 筋力やADLを保つため 安定期には軽い運動 (5〜6 METs程度)が 推奨される |

3.病期にあわせた安静
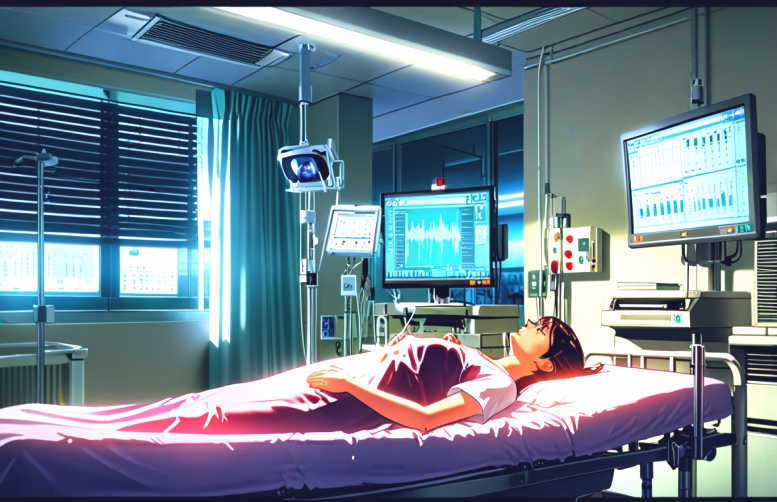
急性期(浮腫・蛋白尿が顕著)
ベッド上安静
(必要時のみトイレ歩行など)
微活動(手の軽い運動など)を
取り入れながら静養を促す
改善期(尿量増加、浮腫軽減)
毎日の体重・浮腫観察、蛋白尿の
推移と照らし合わせながら
運動範囲を調整
軽度の歩行許可
(トイレ・病棟内歩行など)
入浴や日常生活動作も段階的に再開
寛解期(尿タンパク陰性、全身状態安定)
安静の必要なし
長期ステロイド使用による骨粗鬆症
肥満・心血管リスクを踏まえ
ADL維持と体力維持を支援
無理のない日常活動や散歩などは
再発予防にも有効
ただし過労やストレスは避けるよう指導
4.看護のポイント

看護のポイント
浮腫観察とケア
体重測定(毎日同時)
四肢の周囲径測定、圧痕の有無
皮膚の状態
皮膚トラブル・褥瘡のリスク
体位変換と褥瘡予防
浮腫部位を心臓より高く保ち
クッションや枕で下肢挙上を促す
DVT・肺塞栓症の予防
下肢の自動運動、下腿マッサージ
弾性ストッキング着用
呼吸状態、下肢痛、腫脹、SpO₂低下など
感染予防
ステロイドによる免疫低下を考慮し
感染対策を強化
手指衛生の徹底、口腔・陰部ケア
疲労・ストレス管理
エネルギー節約のために休息と
活動をバランスよく行う
患者の精神的ケア
長期間の安静で不安、退屈、抑うつなど
が出現しやすい
コミュニケーションの頻度を増やし
回復への見通しや説明を伝える
患者・家族指導
安静→徐々に活動へ移行する理由を
わかりやすく伝える
改善後も無理な活動や過労を避けること
の重要性を伝える
再発時は医師相談の上安静調整が必要
5.安静実体験

実体験
入院直後からも安静度制限は
ありませんでした
ただ、全身の著明な浮腫と
呼吸困難によって積極的に動くことが
できず結果安静が余儀なくされる
状況でした
安静による腎血流の維持と腎保護への
効果は感じました
ちょっと動きすぎたかなって日は
利尿反応少ない感じでした
ただ、ネフローゼ症候群においては
過度の安静をしたからといって
急激に尿量がふえて、浮腫みが
改善するわけではありません
過度の安静による深部静脈血栓症の
リスクや筋力低下のリスクを考えると
適度な運動が必要とでした
関連記事はこちら

前回の記事はこちら

ネフローゼ症候群と
安静について
お伝えしました
前回記事も
ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき
ありがとうございます
ねふなHappyワークライフ
バランスは現役看護師が
ネフローゼ症候群発症
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や
仕事に悩む方の参考に
なればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする
情報を提供できればと思っています