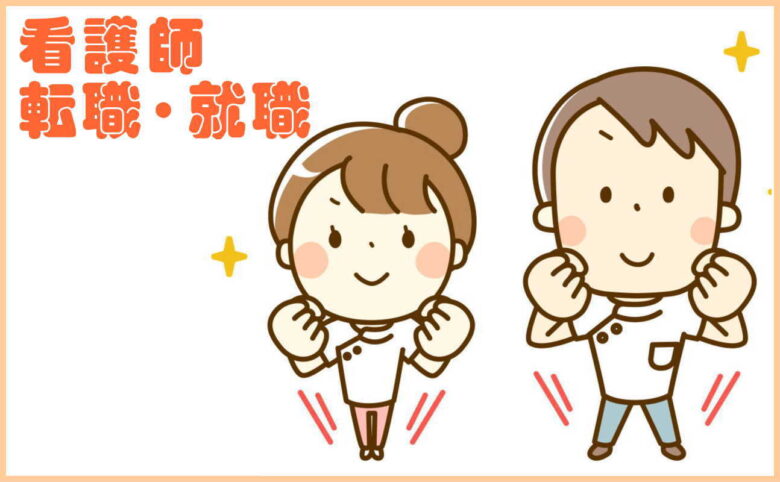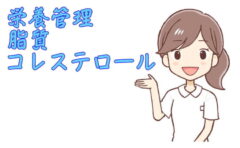こんにちは
看護師ねふなです
病院勤務復職に向け
知識整理中です
栄養管理で
タンパク質について
お伝えします
栄養管理:タンパク質

ネフローゼ症候群になり一時期は
血清総タンパク量3.2g/dL(基準値6.5~8.1g/dL)へ低下して
タンパク質の重要性をひしひしと体感
タンパク質摂取について勉強しなおしました

1.タンパク質

タンパク質
アミノ酸が多数結合した高分子化合物
筋肉や臓器など体を構成する要素として重要
炭水化物・脂質とともに3大栄養素と呼ばれるエネルギー源のひとつ
1gで約4kcalのエネルギーを算出
優先的に組織や酵素、ホルモンの材料として使用
食事から摂取したタンパク質がアミノ酸に分解されてカラダに吸収されると
筋肉や臓器、肌・髪・爪などの材料として使われる
ホルモン・代謝酵素、免疫物質などになりさまざまな働きをする
栄養管理の基礎から具体的症例まで
「認定NSTガイドブック」
2.タンパク質の構成

タンパク質の構成
人体は約10万種類のタンパク質から構成されている
アミノ酸の種類や配列によって違いが生じる
単純タンパク質
アミノ酸からのみつくられる
複合タンパク質
アミノ酸以外の成分も含まれる
必須アミノ酸(9種類)
体内で必要量を合成できないため食事から摂取する必要がある
バリン・ロイシン
イソロイシン・スレオニン
メチオニン・リジン
フェニルアラニン
トリプトファン・ヒスチジン
非必須アミノ酸(11種類)
体内で合成できる
グリシン・アラニン
グルタミン酸・グルタミン
セリン・アスパラギン酸
アスパラギン・チロシン
システイン・アルギニン
プロリン
3.体タンパク質の動的平衡状態

体タンパク質の動的平衡状態
体内のタンパク質は合成と分解がくりかえされている
合成と分解のつり合いをとるには食事からのタンパク質摂取が必要
体タンパク質は新しく作られるが髪や爪が伸びるように抜け落ちて失われるものもある
髪や爪のように目に見えるものだけでなく筋肉や臓器なども一部は分解されて体外へ排泄されている
失われるものを補うためカラダを作る材料であるタンパク質の摂取が必要
4.摂取不足と過剰摂取

摂取不足
免疫機能が低下して細菌・ウイルスへの抵抗力が弱くなる
筋肉量の減少
筋力が低下する
皮膚の美しさや髪のしなやかさが失われる
貧血の原因
過剰摂取
タンパク質が合成分解を繰り返す過程での副産物(窒素)の体外排出のため
腎臓に負担がかかる
脂肪として蓄えられ肥満を招く
吸収されず腸に送られた動物性タンパク質が腸内で悪玉菌のエサになり
増殖を促し腸内環境の乱れにつながる
栄養成分・一日のエネルギー必要量の算出方法についてはこちら

5.タンパク質摂取量

タンパク質摂取量
※食事摂取基準(厚生労働省)
| 年齢 | 摂取エネルギー 蛋白割合 | 男性摂取グラム | 女性摂取グラム |
| 18~49歳 | 13~20% | 65g | 50g |
| 50~64歳 | 14~20% | 65g | 50g |
| 65歳以上 | 15~20% | 60g | 50g |
※必要なタンパク質量は体格や活動量でも変動する
個人に合わせたタンパク質の調整が必要
※フレイル予防
65歳以上では少なくとも体重1kgあたり1.0g/日のタンパク質を摂取することが
望ましいといわれている
高齢者の場合は体重を目安にしたタンパク質摂取も参考になる
関連記事はこちら

前回記事

今回は栄養管理
タンパク質を
おつたえしました
前回記事も
ごらんくださいね♡

最後までご覧いただきありがとうございます
看護師ブログ
ねふなHappyワークライフバランスは
現役看護師がネフローゼ症候群発症し
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や仕事に悩む方の
参考になればと思っています
約10年間異業種で働いた後に
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする情報を
提供できればと思っています