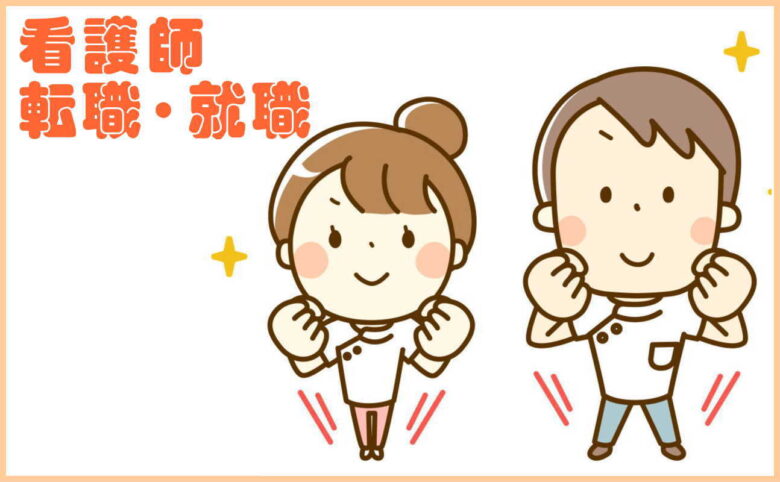こんにちは♡
ねふなです
脳循環に
影響する因子
について
お伝えします

1.脳循環に影響する因子:脳虚血
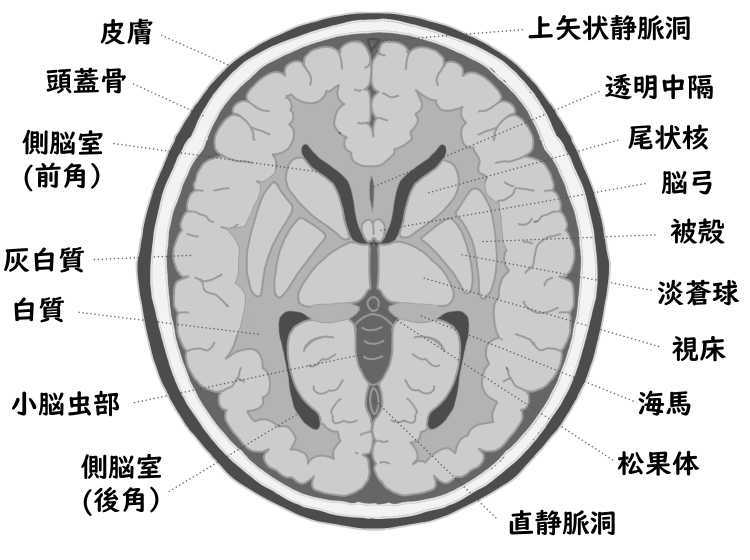
脳の特性
多量の酸素を必要とする
心拍出量の15~20%
全酸素供給量の20%を受けている
通常脳血流量(cerebral blood flow:CBF)
50ml/100g/分
平均動脈圧50~150mmHgの
範囲であればCBFは自動調整能によって
一定レベルに維持されている
臨床的に脳虚血と言われる状態
CBF18-20m1/100g/分以下
CBFが10ml/100g/分以下
ATP枯渇・細胞の脱分極が起こる
この状態が続くと脳の不可逆的な
変性が起きる
CBFに影響を与える因子
脳灌流圧
(cerebral perfusion pressure:CPP)
動脈血酸素分圧(PaO2)
動脈血酸素含量(CaO2)
動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)
血液の粘稠度
高血圧患者の場合
CBFの自動調整範囲が高血圧側に
シフトする為、健常者では正常と
考えられる血圧でも脳虚血を起こす
2.通常脳血流量への影響因子
通常脳血流量
(cerebral blood flow:CBF)
に影響を及ぼす因子
CCPとCBF
CPP
平均動脈血圧と平均頭蓋内圧の差で表す
平均頭蓋内圧ICPの平均は5~15mmHg
50mmHg以下
酸素供給不足により脳は虚血状態になる
PaO2・PaCo2とCBF
貧血の場合ならびにPaO2ga50Torrを
下回った場合CBFは著明に増大する
PaCO2が20~80Torrの場合
1TorrのPaCO2変化に対し
CBFは1~2ml/100g/分の割合で増加
そのため頭蓋内のコンプライアンスが
低ければ、ごくわずかな高二酸化炭素症
でもICPは著明に増加する
CBFと酸素の関係は動脈血酸素含量(CaO2)から
考えると理解しやすい
CaO2は通常16-20ml/dl動脈血で
酸素運搬量(DO2)は8-10mlO2/100ml
動脈血でヘモグロビン濃 度と酸素飽和度との積に比例
CaO2とCBFとは線形関係にあるため
高度の貧血を来すとCBFは劇的に増大
ヘモグロビン解離曲線の形状から考えて
PaO2が約50mmHgを下回るまで
CaO2はほとんど変化しないが
CBFは著明に増大
臨床的にはPaO2が30-35mmHg以下で
脳虚血になると考えられる
仕事選び転職サイトはこちら↓↓
3.通常脳血流量への影響因子
体温とCBF
脳温度を適正に保つことは脳外科手術に
おける脳保護として重要
近年軽度低体温療法が注目されている
低体温になるとCBFは1℃につき
約6%低下する
CMRo2とCBF
脳酸素代謝率
(cerebral metabolic rate of oxgen:CMRo2)
通常3.5ml/100g脳組織
脳代謝はグルコースと酸素に
依存しておりCMRo2に影響を与える
因子としては麻酔薬・体温・痙攣発作が
あげられる
4.水頭症

水頭症
脳脊髄液は脈絡叢で血液から産生される
脳脊髄液の循環障害で最も問題になる
5.脳浮腫
脳浮腫
頭部外傷・脳出血・脳腫瘍など様々な
疾患に付随して発症する
進行すると脳ヘルニアを引き起こし
死につながる可能性があるため
脳浮腫のコントロールは重要
脳浮腫の分類(Klatzo分類)
細胞毒性浮腫
損傷部位:脳細胞
血管透過性変化:亢進
形態学的変化
細胞外腔拡大・アストロサイト膨張
原因疾患
低酸素、代謝異常・水中毒・脳処決初期
血管原性浮腫
損傷部位:脳血管
血管透過性変化:なし
形態学的変化:脳細胞膨張
原因疾患
凍結損傷・外傷・炎症・脳虚血後期

6.脳浮腫機序
脳浮腫機序
発生あるいは進行にアクアポリンの関与
アクアポリン(Aquaporin:AQP)
細胞膜に存在する細孔(pore)を持った
タンパク質
MIP(major intrinsic proteins)に属する
膜内在タンパク質の一種
細胞への水の取り込みに関係し
水分子のみを選択的に通過させる
1.AQP4の働き
存在箇所
脳室周囲、くも膜下腔(軟膜)
視床下部・脈絡膜叢など
アストロサイト(星錠膠細胞)に特に多い
働き
脳脊髄液量調節屋ホルモン分泌に関与
血管と脳の水の移動に関与している
2.AQP1の働き
存在箇所
脈絡膜叢においてAQP4とともに発現
働き
髄液の産生あるいは吸収に関与
7.痙攣の管理
痙攣
脳内の異常な電気放電や電流の異常が
骨格筋に至る運動神経経路を興奮させ
筋肉の急激な不随意運動を起こすもの
痙攣の原因
器質的脳疾患
脳腫瘍・脳血管障害
脳感染症・頭部外傷
機能的脳疾患
水、電解質異常・循環不全
腎不全・肝不全
低血糖・パーキンソン病
ジストニア・痛み
顔面けいれん・三叉神経痛
全身疾患
低血糖・熱性けいれん
破傷風・低酸素血症・中毒・髄膜炎
痙攣発作時
タイプ、持続時間、意識障害を確認
全身性か局所性かを見極める
全身性の場合
気道を確保し直ちに医師へ報告
原因検索を行う必要がある

関連記事はこちら

前回の記事はこちら

今回は
脳循環に
影響する因子
について
お伝えしました
前回の記事も
ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき
ありがとうございます
ねふなHappyワークライフ
バランスは現役看護師が
ネフローゼ症候群発症
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や
仕事に悩む方の参考に
なればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする
情報を提供できればと思っています