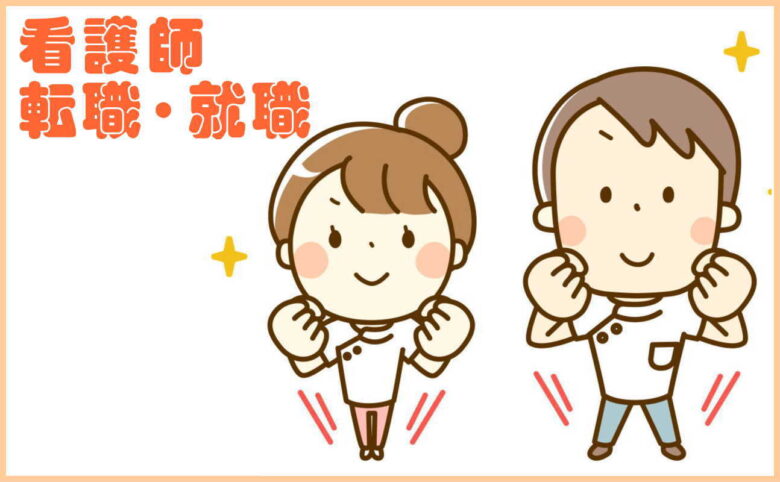こんにちは♡
ねふなです
看護師復職に向け
知識整理をしました
今回は意思決定
支援ツール
臨床倫理4分割法
をお伝えします
意思決定支援ツール:臨床倫理4分割法

患者の意思決定支援の
実践として臨床倫理の
4分割法についてまとめています
「看護倫理よい看護・よい看護師への道しるべ」はこちら↓↓
1.臨床理論の4分割法

臨床倫理の4分割法
現場で治療方針を円滑に決定するための実践的な方法
治療方針決定では、患者を中心に医師・家族・看護師など多様な立場から異なる意向が示され、足並みが揃わないことがある
そのような場合に、4分割法を用いて患者情報を整理・共有し、チームで最善策を検討する

2.臨床倫理の4分割法発展の経緯

ジョンセンによって1992年提唱
医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況という四項目について
必要な情報や問題点を整理して分析をする方法を提案
4つの項目に関連する倫理原則
ビーチャムとチルドレスが示した生命倫理の四原則に対応するもの
| 4分割の項目 | 対応する倫理原則 | 内容 |
| 医学的適応 | 善行・無害 | 医療の有効性、安全性 利益と害の バランスを 判断 医学的に妥当かつ患者にとって利益があるか |
| 患者の意向 | 自立尊重 | 意思決定能力 のある患者の 自己決定権を尊重 インフォームド・コンセント、拒否権の 尊重 |
| QOL | 善行・無害・自立尊重 | 治療によって 得られる生活の質を評価 患者が望む 生活と治療の 方向性が合致 しているか |
| 周囲の状況 | 正義 | 公平な資源配分、法的・社会的枠組み 家族や社会の 影響を考慮 医療の公平性・法的倫理的妥当性 |

3.倫理原則

善行の原則
仁恵や恩恵の原則ともいい患者にとって恩恵となることは
行うべきだという原則
無危害の原則
患者にとって危害となるようなことは
行うべきではないという原則
自律尊重の原則
自己決定権の尊重・患者が自分で考えて判断する自律性を
尊重しなければならないという原則
正義の原則
公平と公正のという意味があり公平な資源の分配
資源を分配する際平等に行うという原則
4.医学的適応

医学的適応
(Medical Indication)
診断と予後
患者の医学的な診断・病状や予後
治療目標の確認
治療の目標と成功の可能性
医学の効用とリスク
治療に失敗した場合の対応
無益性
医療ケアを受けることが患者の利益となるか
5.患者の意向

患者の意向・動向
(Autonomy)
判断能力
判断能力の有無
インフォームドコンセント
利益やリスクの説明を受け理解した上で同意したか
治療の拒否
治療に協力しない・協力できない
事前の意思表示
治療前の意思表示、患者が受けたい治療
代理意思決定
患者の代理で方針を決定する方がいるか
権利の尊重
患者の選択する権利が尊重されているか
6.幸福追求(QOL)

幸福追求:QOL
(Quality of life)
QOLの定義と評価
誰がどのような基準で決めるか
偏見の危険
QOL評価にバイアスがかかっていないか
何が患者にとって最善か
治療した場合・治療しなかった場合の社会復帰の可能性
治療で患者がどのような不利益を被るか
現在・将来の状態は患者にとって苦しい状況となるか
治療を中止する場合、その理由は何か
緩和ケアは受けられるか
QOLに影響を及ぼす因子
7.周囲の状況

周囲の状況
(Contextual Features)
家族や利害関係者
患者の家族の問題
守秘義務
経済的側面、公共の利益
経済的な問題
方法の正当性
施設の方針、診療形態、研究教育
利用する資源
医療関係者側の問題があるか
臨床研究・教育に問題があるか
法律、慣習、宗教
治療決定が法的にどのような
意味をもつか
宗教や文化による問題があるか
その他 (診療情報開示、医療事故)
もっと詳しく知りたい方には
「看護倫理よい看護・よい看護師への道しるべ」はこちら↓↓
関連記事はこちら



前回の記事はこちら

病院勤務復職向け
知識整理をしました
今回は
意思決定支援ツール
臨床倫理4分割法を
お伝えしました
前回の記事も
ごらんください

最後までご覧いただき
ありがとうございます
看護師ブログ:ねふなHappy
ワークライフバランスは
現役看護師が
ネフローゼ症候群発症し
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や
仕事に悩む方の参考に
なればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする情報を
提供できればと思っています