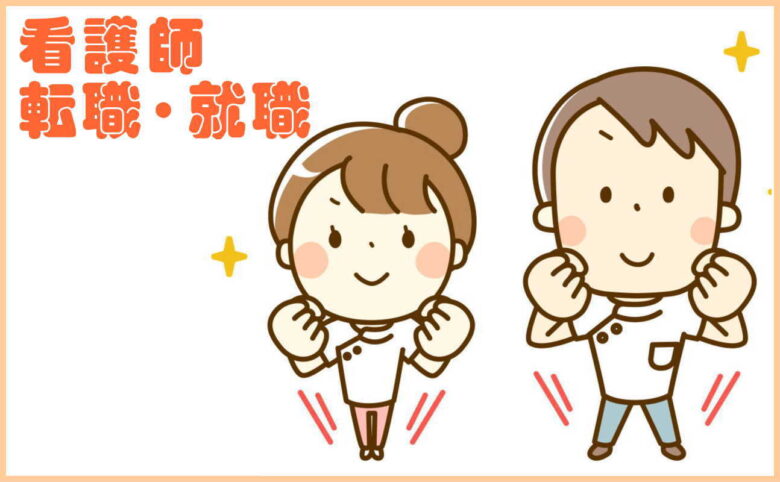こんにちは♡
ねふなです
今回は
ネフローゼ症候群と
夜間利尿について
お伝えします
ネフローゼ症候群と夜間利尿
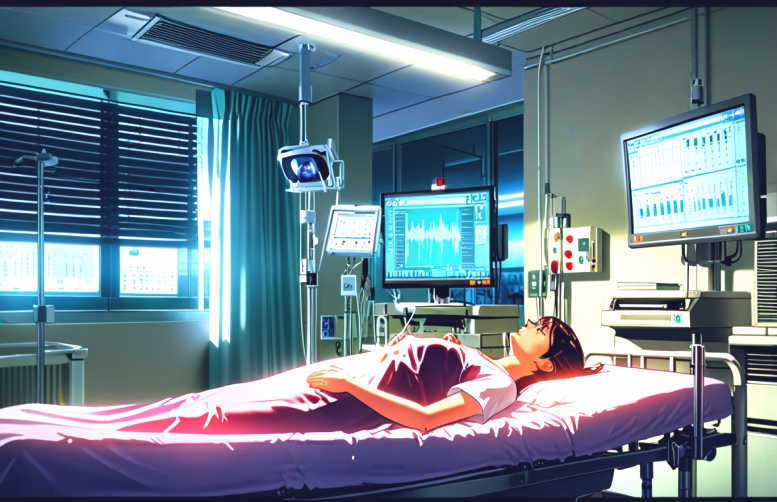
ネフローゼ症候群での
療養生活中の自覚症状として
日中よりも利尿が
増えることがありました
その夜間利尿についてまとめています
1.ネフローゼ症候群
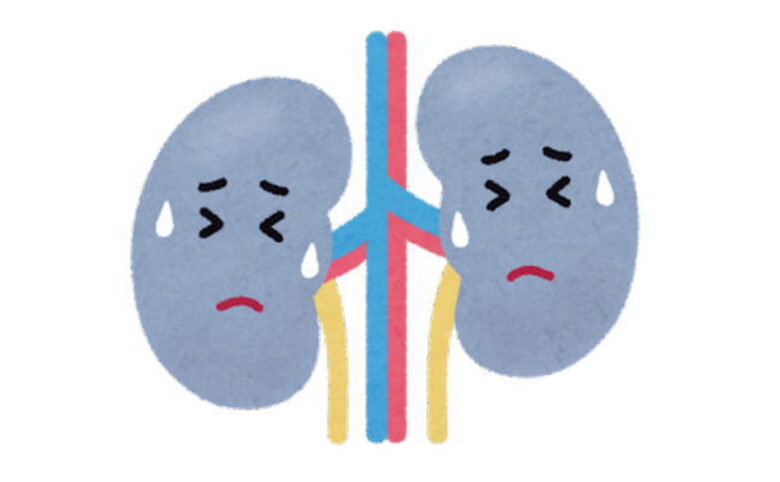
ネフローゼ症候群
蛋白尿(1日3.5g以上)
低アルブミン血症
浮腫・高脂血症を特徴とする腎疾患
糸球体の障害により尿中に蛋白質
が異常に漏れ出すことで
さまざまな症状が現れる
2.夜間尿量増加

正常時利尿
体内リズムによりコントロールされ
睡眠時は覚醒時に比べ排尿しにくい
メカニズムになっている
作用機序
抗利尿ホルモンの分泌が覚醒時の
2倍程度増加し、尿量を60~70%へ
減少させる
副交感神経の緊張がゆるみ膀胱容量を
覚醒時の1.5倍にする
夜間尿量増加(夜間多尿)
夜間に排尿量が増える状態
正常では、夜間は抗利尿ホルモン(ADH)
により尿量は減少する
このバランスが崩れると
夜間の尿量が増える
実体験
夜間は覚醒時の1.5倍は多い印象
3.生理的機序

生理的機序
1.日中の体位と浮腫の形成
大量の蛋白尿から低アルブミン血症と
なり血漿膠質浸透圧が低下
⇒血管内から水分が組織間に移動し
浮腫が生じる
日中は立位や座位が多いため
重力の影響で下肢に水分が貯留
しやすく、浮腫が強く現れる
2.夜間臥床による体液移動(再分布)
夜間・臥床することで重力の影響が減少
⇒下肢に貯留していた間質液が静脈側に
再吸収されやすくなり、血管内に戻る
循環血漿量の増加
3.腎血流量と尿生成の増加
血管内に戻った水分により、腎臓へ
血流が増加し糸球体濾過量(GFR)が上昇
⇒腎臓は濾過された血液から尿を
生成するため尿量が増加する
夜間多尿の主たるメカニズム
4.抗利尿ホルモン(ADH)の影響
本来、夜間は抗利尿ホルモンが分泌され
尿量が抑えられる
ネフローゼに伴う循環血漿量の変動や
浮腫による体液恒常性の乱れが
ADHのリズムを乱す
⇒夜間でもADHが十分に働かない
⇒結果的に尿量抑制が不十分
5.ナトリウム・水分貯留と排出の
リバランス
ネフローゼ症候群ではRAA系やADHの
活性化により日中はナトリウム
水の貯留が優位
⇒夜間、体液の再分布や循環血漿量の
回復によって過剰なナトリウムと
水を排出しようとする働きが強まり
利尿が進む
⇒ナトリウム利尿・水利尿が
夜間に起こる

4.看護のポイント

看護のポイント
観察・アセスメント
尿量と排尿パターンの記録
日中と夜間の尿量・排尿回数の比較
(24時間尿量の記録)
夜間多尿があるか
夜間尿比率(夜間尿量/24時間尿量)把握
33%以上なら夜間多尿の可能性
浮腫の程度と部位
下肢・顔面・体幹など浮腫の分布や
圧痕の有無を確認
浮腫が強い場合は夜間の体液移動による
夜間多尿が起こりやすい
体重・水分出納の管理
1日あたりの体重変化
摂取量・排泄量(in/outバランス)
急激な体重減少がある場合
過度な利尿の可能性を考慮
バイタルサインと腎機能
血圧の変動
低血圧があると脱水のリスク
尿検査
蛋白尿や比重の変化など
ケア・安全管理
転倒予防対策
夜間に頻回の排尿行動があると
転倒リスクが上昇
特に高齢者では、夜間の視界不良や
ふらつきに注意
対策例
夜間用足元灯の設置
看護師コールの導入、促し
排尿の誘導と介助
ベッドサイドにポータブルトイレ設置
失禁も評価
服薬と治療のサポート
利尿薬の投与時間の見直し
医師と連携
看護師から医師へ、服薬時間調整の
必要性をフィードバック
血圧・腎機能に応じた水分管理
飲水制限がある場合
夜間の口渇に対応できる方法を検討
生活指導・患者教育
「なぜ夜に尿が増えるのか?」という
生理的な理由をわかりやすく説明
⇒安心感の提供
自己管理意識の向上につなげる
日中の休息や足の挙上指導
日中にも足を挙げて休むことで
浮腫軽減と夜間多尿のコントロール
が期待できる
睡眠への影響確認
夜間排尿が睡眠を妨げていないか
睡眠の質の評価
関連記事はこちら

前回の記事はこちら

ネフローゼ症候群と
夜間利尿について
お伝えしました
前回の記事も
ごらんくださいね♡

最後までご覧いただき
ありがとうございます
ねふなHappyワークライフ
バランスは現役看護師が
ネフローゼ症候群発症
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や
仕事に悩む方の参考に
なればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする
情報を提供できればと思っています